緑区[1] 中京競馬場前

家族のブロンズ像のタイトルは「大将」-中京競馬場前駅
今回からは緑区を探訪します。名鉄名古屋駅から名鉄名古屋本線の普通列車に乗ります。南区にあった本星崎の駅を越え、天白川、扇川を渡ると緑区に入ります。次の鳴海から左京山、有松、中京競馬場前まで4つの駅が緑区内に設置されています。では緑区の端にある中京競馬場前駅で降りて歩いてみましょう。

▲馬が疾走する姿が描かれた、名鉄名古屋本線中京競馬場前駅
中京競馬場前駅は2001(H13)年にリニューアルされており真新しく、さすが競馬場前ということだけあって、駅舎の壁面に疾走する馬のシルエットが描かれています。そしてやはり登場のブロンズ像。
中央に子どもが座り、その子から見て右に父親、左に母親が座っている像が置かれています。子どもは黄金で折られた兜をかぶり、両手を挙げて喜んでいます。そして父親は何かを指差しています。そして母親は少し呆れ顔。これってひょっとして…。

▲「大将」。競馬場にやってきた親子の姿?
「よ~し、あの馬が1着で入ったらおもちゃ買ってやるぞ~。」「わーい。」なんていう、競馬場の昼下がりを再現したブロンズ像なのかも。いや、たぶん違いますね。ちなみにその像のタイトルは「大将」でした。「うちの子は我が家の大将。」そんなところです。
豊明市にある今川義元戦死の地-桶狭間古戦場
今回は、この中京競馬場前駅から南へと歩きます。名鉄名古屋本線の南側を並走する、国道1号が名古屋市の市境になっているので、豊明市地内へと行くことになります。「名古屋を歩こう」なのに豊明?と思われるかもしれませんが、どうしても話を展開する上で見ておきたい場所がそこにあるのです。

▲国道1号より、この高徳院の看板の手前を南へ
国道1号線に出ると「高徳院」という大きなお寺の案内看板のある道があるので、そこを南方向へ曲がります。そして桶狭間病院と藤田学園本部を越えると、左手に公園が見えてきます。「桶狭間古戦場」です。

▲目の病気に強い藤田学園本部の南側に古戦場が広がります
1560(永禄3)年5月19日(新暦6月12日)、駿河の大名・今川義元は、既に三河までを手中に収め、2万5千の兵を引き連れて尾張に侵攻しました。
対して尾張の大名・織田信長はわずか3千の兵でありながら、雨の中、今川義元の旗本部隊に奇襲作戦を決行し、今川義元を討ち取りました。これにより今川氏はそれまでの勢いを失い没落してしまいます。

▲庭園かのように整備された古戦場
その戦いが行われたのが、ここ「桶狭間古戦場」と言われています。当時は「田楽挟間」「舘挟間」と呼ばれていました。公園内には様々な史跡が残されています。

▲今川義元の戦死を示す最も古い石碑。1771(明和8)年製
かつては今川義元や松井宗信、そして無名な人々の塚があるだけだったのですが、1771(明和8)年12月に鳴海下郷家の出資によって七石表が建てられました。これが、今川義元がここで戦死したことを示す最も古い石碑です。
北面には「今川上総介義元戦死所」、東面には「桶狭七石表之一」、そして南面には「明和八年辛卯」とあります。

▲桶狭七石表之一の文字
さらに1809(文化6)年5月には津島神社の社司によって桶狭間弔古碑が建立され、1876(M9)年には有松に住んでいた山口正義という人物が主唱し、今川治部大輔義元(いまがわじぶだゆうよしもと)の墓が建てられています。

▲1809(文化6)年5月に建てられた桶狭間弔古碑
そして1937(S12)年12月21日には、この桶狭間古戦場が国の指定史跡となっています。

▲かつては塚だった場所に建てられた、今川治部大輔義元の墓
それにしても不思議なのは、ここで桶狭間の戦いが繰り広げられ今川義元が命を落としたことから、それを弔ったり、お墓を建てることは当然だと思うのですが、わずかな兵でありながらその今川軍を打ち破った織田信長の功績を称える史跡が全く無いという点です。

▲県によって建てられた、桶狭間古戦場であることを示す石碑
豊明市教育委員会の資料を見ても「信長に襲われ」「信長の奇襲に遭い」といった表現ばかりで、どうも豊明市はここを「桶狭間の古戦場」というより、「今川義元戦死の地」という位置付けにしている気がしてなりません。

▲江戸時代の歌人、香川景樹が自分の運命を義元になぞらえ詠んだ句碑
実はそこに、大きな問題が隠れていたのです。それは後ほど明らかになります。

▲今川、織田両軍の動きを示す看板。もちろんこの地が「決戦場」
この古戦場公園の東側にある、オキタ商店の手前の急な坂道を登っていきますと桶狭間市民緑地があり、その先に桶狭間社という神社があります。

▲急坂を登っていきます
坂は本当に急で、歩いただけで息切れをしてしまうほどです。その甲斐あってか、桶狭間社からの眺めは絶景。

▲さらに階段の上にある桶狭間社
信長軍は、こうやって丘の上から今川軍の動きを察知し、奇襲作戦を決行したのかなと想像ができます。しかし、実際に信長軍がどこから奇襲作戦を仕掛けたかという資料は残っていないそうです。それどころか…。

▲桶狭間社からは周囲が一望できます
今川義元の本陣跡-高徳院
さて、今度は古戦場公園の西側にある道を南下します。すると右手に、先程看板があった高徳院があります。ここは今川義元の本陣跡といわれています。

▲今川義元の本陣跡といわれる高徳院
かつては古戦場資料館があったそうなのですが、現在はどうも無くなってしまったようでした。なので高徳院の南側の道路を西へ西へと歩いていきます。
この時は道路工事が行われていて「この工事は日本中央競馬会の補助金が使われています」という、地域性のよく表れた看板が登場しました。
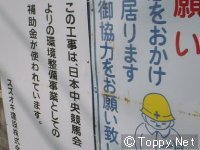
▲競馬場さまさま
そのまま西へ歩いていくと緑区に戻ります。道路の舗装が急に良くなるところから名古屋市です。わかりやすいですね。そこは緑区桶狭間北。住所が桶狭間になりました。
すると、また「桶狭間古戦場公園」が登場しました。もちろん先程の公園とは場所が違います。こちらは名古屋市内です。説明看板には「この地が歴史に云う桶狭間合戦の古戦場で今川義元戦死の地であります。」とあります。どういうこと…?

▲あれ、古戦場がまたある?
実は、信長軍がどこから奇襲作戦を仕掛けたかだけではなく、桶狭間の戦いがどこで行われたかという資料自体が残っていないのです。そのため二つの古戦場が誕生してしまったのです。
豊明市の史跡には今川義元のお墓がありました。名古屋市側の古戦場には何があるので
しょうか。次回です。





コメント