西区のなりたち
西区プロフィール
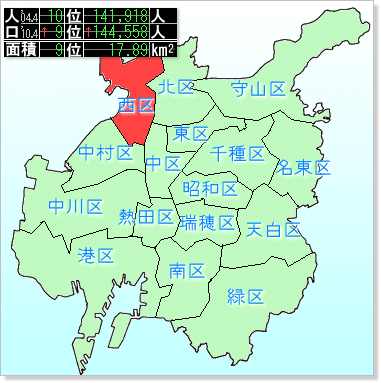
![]()
名古屋の城下街
西区は、古くから城下町として栄えたお城から庄内川にかけての名古屋城北西部一帯と、庄内川の北側・小田井地区をエリアとする区です。名古屋市が市制施行をした1889(M22)年当初は、名古屋城近くの一部分が含まれていただけで、残りは郡部でした。
那古野村と枇杷島町
1898(M31)年には那古野村が名古屋市に編入され、1908(M41)年に区制が施行されると当時の旧西区はこの一部分と現在の中区、中村区、北区のそれぞれ一部を含む形となりました。そして 1921(T10)年、庄内川よりも東の枇杷島町が旧西区に編入されました。東枇杷島が名古屋市なのに対し、庄内川の西にある西枇杷島は現在も西春日井郡西枇杷島町として独立しています。
金城村と庄内村
そして1921(T9)年に児玉や押切の北側が金城村から旧西区に、1930(S5)年と1937(S12)年の2回にわたり庄内村が名古屋市と合併し、庄内川の内側の部分全てが旧西区となり、広範囲の区となります。
そのため1944(S19)年に区域が改められ、旧西区のうち、現在中区の部分は当時新設の栄区に、北区、中村区の部分についてはそれぞれ各区に分けられ、庄内川の南側については現在の西区の姿となります。
山田村も編入
庄内川の北側にあった山田村は 1955(S30)年に西区に編入され、現在の西区の形が完成します。ですので、西区のなかでも庄内川よりも北側は比較的新しい名古屋市域と言えます。そこには歴史的にも微妙な温度差があります。
現在の西区の範囲はこのような変遷をたどっていますが、かつては現在の中区、中村区、北区の部分も西区とされていた部分がありました。なりたちは現在の区分で辿っていますので、そのあたりは各区でご紹介しています。
西区のみどころ-食品から食器、車・名古屋製造業の原点
西区の南部は名古屋駅の一部までもが含まれていて、かつての名古屋城下町風情を今も残しています。堀川の西岸にある「四間道」は町並み保存地区に指定されていて、芸者町だった面影もあります。
屋根神さま
また名古屋独特の信仰スタイルである、長屋の2階にあげられている小さな社「屋根神さま」も多く見られます。度々お参りに行くことができない人々が、普段からお参りできるようにと家に社を祀ったものです。戦火で多くが焼失してしまったそうですが、建物は無く今は屋根神さまだけが姿を残しているところもあります。
世界に羽ばたく自動車・陶磁器に駄菓子
また、このあたりは駄菓子の生産・取引が盛んで、ここから全世界に向けて出荷されています。お菓子メーカーとして有名なあのメーカーも本社を構えています。名古屋城から西側一帯は、そういったものづくりの街です。
トヨタ自動車発祥の地でもあり、こちらも世界的に有名な陶磁器メーカー「ノリタケ」の工場もあります。また産業のテーマパークもあり、名古屋製造業の原点を見ることができます。
信長や秀吉が幼少期に駆け回っていた…
庄内川の手前、稲生地区は織田信長が勝利を収めた稲生ヶ原の合戦の舞台。もちろんその痕跡は至るところに残されています。信長や秀吉が幼い頃川遊びをしたと言われる庄内川の北側には洗堰緑地という場所があるのですが、これはここ最近できたものではなく歴史があります。
川とともに歩んできた歴史の痕跡
そこには庄内川の南側である名古屋城下とその北側、小田井地区との差別の歴史が残されています。それは今だ解決されておらず、対策が進められています。その緑地の意味とは、そして庄内緑地公園の本当の設置目的とは一体何なのでしょうか。
そして枇杷島から小田井、岩倉を結んだ岩倉街道には今も歴史を感じさせる建物が残り、こちらも町並み保存地区となっています。このあたりには庄内川の氾濫を防ぐための住民の信仰が厚く、それを物語る神社やお寺がたくさんあります。
城下町、名古屋の産業の原点、そして庄内川の堤防に隠された秘密を見に西区を歩きましょう。
MAP
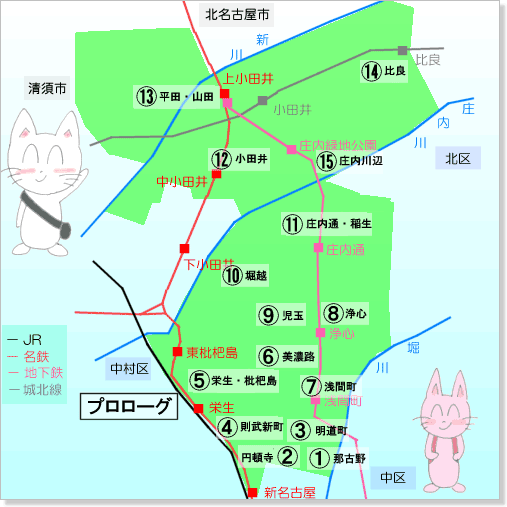
プロローグ 1.那古野 2.円頓寺 3.明道町 4.則武新町 5.栄生・枇杷島 6.美濃路 7.浅間町 8.浄心 9.児玉 10.堀越 11.庄内通・稲生 12.小田井 13.平田・山田 14.比良 15.庄内川辺





コメント